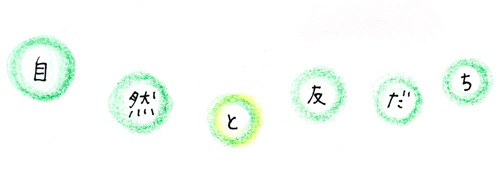
No.81 「冬の宝さがし」
暦のうえでは、立春・・・でも、まだまだ寒い日の続いているこの頃です。冬来りなば春遠からじ・・・の心境でフィールドを散歩してみると、日だまりの草地に小さな花を見つけたり、若草も伸びはじめたり、と早春の訪れを感じます。なんと少し暖かい日には、冬眠中のチョウもめざめて飛び出し、日だまりで日光浴をしているところにも出会いました。また、冬のみに出現するガ、フユシャクにも出会いました。まさに冬の宝さがしは楽しいものです。撮影・解説:松田邦雄
 |

松田邦雄先生に質問やメッセージをどうぞ。
http://www3.jsf.or.jp/mlmaster/
 日の入り
日の入り














