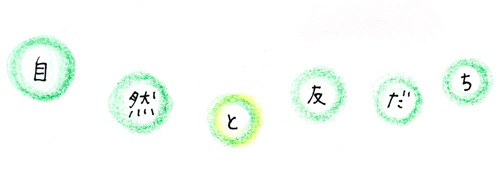
No.99 「猛暑・夏の生きものたち」
連日の猛暑、さすがに虫たちも日なたを避け、木かげに避難するチョウやトンボの姿も見られました。夏の虫、トンボ、セミ、カブトムシの生きる姿をはじめ、草木の花の様子もとらえました。撮影・解説:松田邦雄
 |

松田邦雄先生に質問やメッセージをどうぞ。
http://www3.jsf.or.jp/mlmaster/
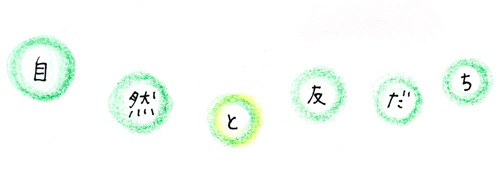
 |

| サルスベリ キョウチクトウ クサギ |
|||||
 | |||||
|
|||||
| 真夏の光に映えるサルスベリ、キョウチクトウ、クサギなどの木の花がよく見られます。 |
| キツネノカミソリ ウバユリ ヤブカンゾウ |
|||||
 | |||||
|
|||||
| ヒガンバナの仲間で、ヒガンバナより1か月ほど早く林の中に咲くキツネノカミソリ、白いユリの花をたくさん咲かせるウバユリ、オレンジ色のヤブカンゾウなどが晩夏の野を飾っていました。 |
| カワラナデシコ オミナエシ |
||||
 | ||||
|
||||
| 晩夏の草原で美しいカワラナデシコ、黄色い小さな花をたくさんつけたオミナエシを見つけました。 |
| キヌガサソウ クルマユリ ニッコウキスゲ |
||||
 | ||||
|
||||
| 信州の栂池(つがいけ)高原では、ふだん見慣れない高原の花が咲いていました。 一面に色とりどり咲く高原の花、さわやかな風がわたり、心も和みます。 |
| ワタスゲ ヒオウギアヤメ カラマツソウ |
||||
 | ||||
|
||||
| まるで綿毛のようなワタスゲ、紫の色鮮やかなヒオウギアヤメ、細かい白い花がいっぱいのカラマツソウ、・・・高原の花がいっぱいでした。 |
| ナガサキアゲハ カラスアゲハ ミヤマカラスアゲハ |
|||||
 | |||||
|
|||||
|
南の館山では、大型のナガサキアゲハ(メス)に出会いました。 また、信州の高原の水たまりのある山路では、カラスアゲハ(左)とミヤマカラスアゲハ(右)が吸水していました。 |
| エルタテハ コムラサキ アサギマダラ |
|||||
 | |||||
|
|||||
|
高地でのみ見られるエルタテハも石垣にとまり、はねをいっぱいに開いてくれました。 コムラサキがさっと飛来して車にとまりました。 ヒヨドリバナにはまるで夢のチョウのように、美しいアサギマダラが吸密していました。 |
| ルリタテハ オオウラギンスジヒョウモン サカハチチョウ ヒメキマダラヒカゲ |
|||||
 | |||||
|
|||||
|
ルリタテハはふつうクヌギなどの樹液のところで見かけますが、なんとヒマワリの花を訪れていました。 ブッドレアーの花には、オオウラギンスジヒョウモン、山道の葉上には、サカハチチョウがはねをひろげて美しい模様を見せてくれました。 ヒヨドリバナの花上で吸密中のヒメキマダラヒカゲの姿も見られました。 |
| ウラギンシジミ アカボシゴマダラ |
|||||
 | |||||
|
|||||
|
ウラギンシジミがさかんに飛びまわっては、なにかにとまり、じっとしていました。なんとミミズの死体にとまって吸汁していました。 最近よく見かける中国からの移入種とみられるアカボシゴマダラも葉上にはねをひろげて休んでいました。 |
| シャチホコガ モンクロシャチホコ オオミズアオ ウンモンスズメ |
|||||
 | |||||
|
|||||
| 木の幹にぴったりはりついていたのは、シャチホコガでした。また、金網にぴたっと静止していたのは、モンクロシャチホコでした。ガは昼はこのように静止している種類が多く、夜には灯りのまわりにオオミズアオやウンモンスズメなど大きなガも飛びまわっています。 |
| ヤママユ マユ |
||||
 | ||||
|
||||
| 信州では、天蚕(てんさん)農家といって、野生のヤママユを飼って淡緑黄色の美しい大きなまゆをとって、美しい織物などをつくって売っている方がいました。まさに日本の伝統文化です。 |
| ギンヤンマ 産卵 ヤブヤンマ 産卵 |
||||
 | ||||
|
||||
| 夏には多くのトンボが見られます。なかでも大型のヤンマは人気が高いです。田んぼでギンヤンマのおすめすが連結しながらスイレンの葉に産卵している姿を発見!!また、山中の小さな池のまわりの石についているコケに産卵中のヤブヤンマも発見。シャッターを切りました。 |
| マルタンヤンマ | ||||
 |
||||
|
||||
| なんと美しいヤンマ!!青く光る大きな目、胸部の鮮やかな青、池畔の木の枝にじっと静止していたのは、珍種マルタンヤンマのオスでした。 |
| カトリヤンマ 羽化 カトリヤンマ |
||||
 |
||||
|
||||
| 館山のトンボ少年・齋藤舜貴君は、家の玄関に置いた水槽でたくさんのヤゴを飼っていました。夜中にカトリヤンマが羽化しました。翌朝、カトリヤンマを屋外に放すと・・・近くの木の枝にとまりました。さっそく近づいてシャッターを切りました。 |
| オニヤンマ コオニヤンマ ウチワヤンマ |
|||||
 |
|||||
|
|||||
|
日本最大のヤンマは、黒と黄の鮮やかなオニヤンマです。すっと目の前をよぎり、草にぶらさがるようにとまりました。 コオニヤンマはヤンマの仲間とはちがい、サナエトンボの仲間です。石の上にはうようにとまっていました。 やはり、ヤンマと名がついているけれど、木の枝の上に水平にとまっているウチワヤンマです。 トンボは種類によって、とまり方が決まっているようです。 |
| ヒメアカネ リスアカネ |
||||
 |
||||
|
||||
|
これはたいへん稀な種類のヒメアカネに出会いました。とても小型のアカネトンボの仲間です。 森の木の枝のうえにリスアカネを発見しました。 |
| チョウトンボ ハグロトンボ |
|||||
 |
|||||
|
|||||
| トンボのはねは、透明なのが普通ですが、黒いはねのトンボもいます。まるでチョウのようにひらひらと黒いはねをひらめかせて舞うチョウトンボ、川辺の砂地に黒いはねと青い体を光らせてとまるハグロトンボなどです。 |
| ヒメハルゼミ アブラゼミ ニイニイゼミ ミンミンゼミ ツクツクボウシ |
|||||
 |
|||||
|
|||||
| 夏の虫、セミの声はかなり遠くまで響いてきます。千葉では、ヒメハルゼミを見つけました。アブラゼミ、ニイニイゼミ、ミンミンゼミ、ツクツクボウシの声はどこでも聞かれました。 |
| カブトムシ ノコギリクワガタ ガムシ カナブン |
|||||
 |
|||||
|
|||||
|
夏の虫の王様、カブトムシ・クワガタは子どもにも大人にも大人気です。近くのクヌギの木でカブトムシ、ノコギリクワガタに出会えました。 木の樹液にはカナブンも集まっていました。夜の燈火に水生昆虫のガムシが来ていました。 |
| アオオサムシ ヘイケボタル |
||||
 | ||||
|
||||
| アオオサムシという甲虫がいます。緑色をしているのがふつうですが、千葉の館山では、赤味を帯びたアオオサムシを見つけました。夜間車を走らせていたら、林のなかになんとホタルのあかりが・・・ヘイケボタルの灯りでした。 |
| カマキリとバッタ オオアメンボ |
||||
 | ||||
|
||||
| ススキの葉になんと3匹のバッタが・・・。ところが、これはバッタの死体で、カビにやられて死んでいました。そこへコカマキリがエサ発見とばかりに近づきましたが、動かない死体に気づいたのか、おそうことはありませんでした。カマキリは動くえさしかとらえません。 池には大型のオオアメンボを見つけました。 |
| 『自然と友だち』バックナンバーはこちら 『北の丸公園の自然HP』バックナンバーはこちら 『自然との出会いHP』バックナンバーはこちら |